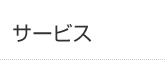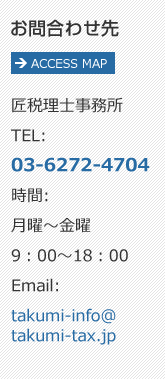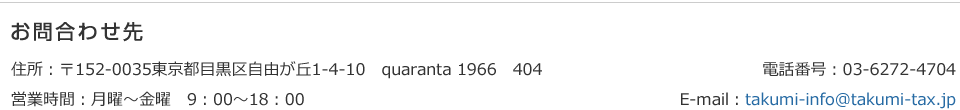中小企業の節税、退職金準備、資金確保に有効的です。
制度のあらまし
制度の趣旨
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
加入資格
(1) 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合及び農事組合法人の役員
掛金
毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円単位で選択することができます。
掛金が全額所得控除になることについての節税額の一例
掛金が全額所得控除になるということですが、どのくらい減税になりますか。
契約者の方の所得金額及び1年に納付する掛金額によって、節税になる額は異なりますが、一例を示せば下記のとおりとなります。
〔例〕掛金の全額所得控除による節税額一覧表
| 課税される所得金額 | 加入前の税額 | 加入後の節税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額5万円 | 掛金月額7万円 |
|
| 200万円 | 102,500円 | 204,000円 | 20,500円 | 56,500円 | 92,500円 | 128,500円 |
| 400万円 | 372,500円 | 404,000円 | 36,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 238,000円 |
| 600万円 | 772,500円 | 604,000円 | 36,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 252,000円 |
| 800万円 | 1,204,000円 | 804,000円 | 39,600円 | 118,800円 | 198,000円 | 277,200円 |
| 1,000万円 | 1,764,000円 | 1,004,000円 | 51,600円 | 154,800円 | 258,000円 | 361,200円 |
※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除をした額で、課税の対象となる金額をいいます。
※2 税額は、平成19年1月1日現在の税率に基づき算定しています(定率減税は考慮していません)。住民税均等割については、4,000円としています。
共済金又は解約手当金をお受け取りいただける場合
共済金又は解約手当金は、どのような場合に受け取れるのでしょうか。
共済金又は解約手当金は、次の場合に、契約者又は遺族の方からのご請求によりお受け取りいただけます。
●個人事業主の場合
(1)A共済事由(共済金A)
事業を廃止したとき又は死亡したとき
(2)B共済事由(共済金B)
老齢給付(満65歳以上で15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金を請求した場合)
※ただし、掛金納付月数が6か月未満の場合には、共済金A又は共済金Bはお受け取りいただけません。
(3)準共済事由(準共済金)
1.配偶者や子供に事業の全部を譲渡した場合
2.個人事業を現物出資により法人成りし、その会社の役員とならなかった場合
(4)解約事由(解約手当金)
1.任意解約(上記(1)~(3)の共済事由が生じないで、契約者の方の申し出によりいつでもできる解約)
2.12か月分以上の掛金の納付を怠ったことなどにより、中小機構が共済契約を解除する中小機構解約
3.現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)
※ただし、準共済金又は解約手当金は、掛金納付月数が12か月未満の場合にはお受け取りいただけません。
●会社等役員の場合
(1)A共済事由(共済金A)
会社等が解散したとき
(2)B共済事由(共済金B)
1.病気やけが、死亡により役員を退任したとき
2.老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金を請求した場合)
※ただし、掛金の納付月数が6か月未満の場合には共済金A又は共済金Bはお受け取りいただけません。
(3)準共済事由(準共済金)
1.役員を任意退任した場合(会社等の解散、病気やけが、死亡以外の理由による退任)
(4)解約事由(解約手当金)
1.任意解約(上記(1)~(3)の共済事由が生じないで、契約者の方の申し出によりいつでもできる解約)
2.12か月分以上の掛金の納付を怠ったことなどにより、中小機構が共済契約を解除する中小機構解約
※ただし、準共済金又は解約手当金は、掛金納付月数が12か月未満の場合にはお受け取りいただけません。
〔例〕基本共済金等の額
(掛金月額10,000円で、平成16年4月以降加入された場合)
| 月数 | 掛金合計額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 |
| 10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 |
| 15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 |
| 20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 |
| 30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 |
解約手当金の額の算定方法(計算例付)
解約手当金は、共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12か月以上のときにお受け取りいただけます。また、お受け取りいただける解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額です。納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月(20年)以上からです。
お受け取りいただく共済金等は、税法上次のように取り扱われます。
| 種類 | 税法上の取扱い | 確定申告の必要の有無 |
|---|---|---|
| 共済金 (除く死亡時) 一括受取り |
退職所得扱い | ・源泉徴収しますので原則不要 ・「共済金等請求書」の提出と同時に、「退職所得申告書」の提出が必要 |
| 共済金 (除く死亡時) 分割受取り |
公的年金等の雑所取扱い(注1)(注2)(注3) | ・源泉徴収として一律7.5%徴収します ・確定申告が必要(毎年1月に源泉徴収票を送付します) |
| 共済金(死亡) | みなし相続財産として相続税の課税対象(死亡時退職金) | ・相続財産として申告が必要 |
| 準共済金 | 退職所得扱い | ・源泉徴収しますので原則不要 ・「共済金等請求書」の提出と同時に、「退職所得申告書」の提出が必要 |
| 解約手当金 (任意解約)65才以上 |
退職所得扱い | ・源泉徴収しますので原則不要 ・「共済金等請求書」の提出と同時に、「退職所得申告書」の提出が必要 |
| 解約手当金 (任意解約)65最未満 |
一時所得扱い | ・一定額以上の解約手当金は確定申告が必要(注4) |
| 解約手当金 (任意解約以外) |
一時所得扱い | ・一定額以上の解約手当金は確定申告が必要(注4) |
(注1) 分割共済金における公的年金等の雑所得扱いとは....
その年中にお受け取りいただいた分割共済金にその他の公的年金額を加えた額から「公的年金等控除」の額を差し引いた額が課税対象となります。
(注2) 分割で共済金をお受け取りいただく場合に未返済の貸付金、未納掛金等がある場合は、共済金からこれらの額を控除しますが、その控除額は一括受取り共済金となり、税法上の扱いも同等になります。
(注3) 繰上げ受取りされる分割共済金は、退職所得扱いとなります。(死亡の場合は相続財産となります)
(注4) 一時所得扱いの場合は、一時所得の金額の計算上、納付した掛金の総額は、支出した金額に算入できません。(ただし、現物出資により法人成りしその法人の役員に就任した場合は退職所得扱いとなります)
契約者貸付制度の貸付条件 (限度額・金利等)
貸付制度について、その概要と資格要件を説明してください。
一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け・緊急経営安定貸付けの貸付条件は、次のとおりです。
なお、一般貸付以外の貸付をご希望される方は、事前に小規模企業共済融資課
(代表:03-3433-8811)にご連絡下さい。
| 一般貸付け | 傷病災害時貸付け | 創業転業時貸付け | |
|---|---|---|---|
| (1)貸付限度額 | 掛金の範囲内です。納付月数により、掛金の7割~9割となります | ||
| 貸付額(上限) | 1,000万円 | 原則1,000万円 | 1,000万円 |
| 貸付額(下限) | 10万円以上 | 50万円以上 | 50万円以上 |
| 併せ貸しの場合 | 複数の契約者貸付けを併せて借りる場合は、1,500万円が上限となります。 | ||
| (2)貸付金の使途 | 事業資金(運転・設備)事業関連資金 | 事業資金(運転・設備) | 事業資金(運転・設備) |
| (3)貸付期間 | 1.貸付額100万円以下6か月又は12か月 2.貸付額105 ~300 万円6か月、12か月、24か月 3.貸付額305万円~500万円、6か月、12か月、24か月又は36か月 4.貸付額505万円以上6か月、12か月、24か月、36か月又は60か月 |
1.貸付額500万円以下36か月(3年) 2.貸付額505万円以上 60か月(5年) |
1.貸付額500万円以下36か月(3年) 2.貸付額505万円以上 60か月(5年) |
| (4)償還方法 | 1.貸付期間が6か月と12か月は、期限一括償還 2.貸付期間が24か月と36か月及び60か月は、6か月ごとの元金均等割賦償還 |
6か月ごとの元金均等割賦償還 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 |
| (5)利率 | 1.5% (平成16年4月1日以降) (金利情勢等を踏まえて設定) |
0.9% (平成16年4月1日以降) (金利情勢等を踏まえて設定) |
0.9% (平成16年4月1日以降) (金利情勢等を踏まえて設定) |
| (6)利息支払方法 | 1. 期限一括償還 貸付時一括前払い 2.割賦償還 貸付時及び償還時に6か月分前払い |
貸付時及び償還時に6か月分前払い | 貸付時及び償還時に6か月分前払い |
| (7)延滞利子 | 年14.6% | 年14.6% | 年14.6% |
| (8)担保・保証人 | 不要 | 不要 | 不要 |
| (9)申込受付期間 | 代理店の営業日に随時受付 | 傷病 入院した日から6か月以内 激甚災害 理事長が別に定める期間 一般災害 一般災害が発生した日から6か月以内 |
事由発生日から1年以内又は事由発生予告日前6か月から |
| (10)借入窓口 | 登録した代理店 (登録申出がない場合は商工組合中央金庫の本店または支店) |
商工組合中央金庫の本店又は支店 | 商工組合中央金庫の本店又は支店 |
| 新規事業展開等貸付け | 福祉対応貸付け | 緊急経営安定貸付け | |
|---|---|---|---|
| (1)貸付限度額 | 掛金の範囲内です。 (納付月数により、掛金の7割~9割となります) |
||
| 掛金の範囲内です。 (納付月数により、掛金の7割~9割となります) |
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 貸付額(下限) | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円以上 |
| 併せ貸し の場合 |
複数の契約者貸付けを併せて借りる場合は、1,500万円が上限となります。 | ||
| (2)貸付金の使途 | 事業資金(運転・設備) 事業関連資金 |
福祉資金 | 事業資金(運転・設備) |
| (3)貸付期間 | 1.貸付額500万円以下 36か月(3年) 2.貸付額505万円以上 60か月(5年) |
1.貸付額500万円以下 36か月(3年) 2.貸付額505万円以上 60か月(5年) |
1.貸付額500万円以下 36か月(3年) 2.貸付額505万円以上 60か月(5年) |
| (4)償還方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 |
| (5)利率 | 0.9% (平成16年4月1日以降) (金利情勢等を踏まえて設定) |
0.9% (平成16年4月1日以降) (金利情勢等を踏まえて設定) |
0.9% (平成16年4月1日以降) (金利情勢等を踏まえて設定) |
| (6)利息支払方法 | 貸付時及び償還時に6か月分前払い |
貸付時及び償還時に6か月分前払い | 貸付時及び償還時に6か月分前払い |
| (7)延滞利子 | 年14.6% | 年14.6% | 年14.6% |
| (8)担保・保証人 | 不要 | 不要 | 不要 |
| (9)申込受付期間 | 事業多角化又は新規開業計画予定日前の6か月以内 | 改築等又は購入計画日前の6か月以内 | 売上高が減少した最近3か月間又は6か月間として算定された翌日から3か月以内 |
| (10)借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店又は支店 | 商工組合中央金庫の本店又は支店 | 商工組合中央金庫の本店又は支店 |
(注1)傷病災害時貸付けの貸付限度額
共済契約者(会社等の役員であるときは、その会社等)が前年度確定申告書に添付した決算書に基づき次の計算を行って得た額が1,000万円を超えるときは、この計算を行って得た額。
[計算式]
(流動負債-当座資産)+1/2(給与+賃金+その他の経費)
(注2)賃付利率について
最新の貸付金利は、テレホンサービス(03-3432-1199、または06-6940-3741)の質問番号185で確認できます。