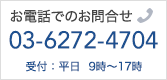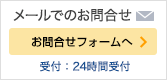匠税理士事務所では、
渋谷区や港区を中心にIT事業のサポートを行っております。
IT事業を経営されている方から頂くご質問の中に、
【 バージョンアップ(VERUP)を行った場合の会計処理はどうなるの? 】
このようなご質問がございます。
そこで今回は、
IT事業におけるバージョンアップ(VERUP)の会計処理についてまとめてみました。
ソフトウエアのバージョンアップの規模で処理が異なる?
バージョンアップは、著しい改良に該当するかどうかで会計処理が異なります。
製品の大部分を作り直す大幅なバージョンアップにかかる費用は、
研究開発費として計上します。
機能を追加したり操作性を向上させたりする大幅でないバージョンアップは、
既存の製品の価値を高め、残存有効期間を延ばす効果が見込まれるため、
資本的支出として資産計上することになります。
そして、すでに完成している製品の未償却残高と合算して
減価償却されることとなります。
ソフトウェア内蔵の機器の会計処理はどうなる?
ソフトウェアの中には、
産業機械やデジタル家電、カーナビゲーション、携帯端末等には専用のソフトウェアが組み込まれて機器と有機的一体として機能するものがあります。
ソフトウェアは機器に組み込まれ、
単体での販売を意図していないものであっても、
製品マスターを複写し、
それを機器に組み込んで販売するのであれば、
市場販売目的のソフトウェアに準じた会計処理を行います。
なお、機器に組み込むソフトウェアの制作だけを
受託している場合には受注制作のソフトウェアの会計処理を行います。
→ 受注案件納品時に、売上と原価を認識することになります。
また自社内で利用する機器に組み込むソフトウェアを制作するような場合には、
自社利用のソフトウェアの会計処理が必要となります。
→ 5年で減価償却を通じて費用化。
ただし、購入者側においては、通常は機器とソフトウェアとを区分することが難しいので
両社を一括して処理することとなります。
ソフトウェアが古くなった場合の廃棄による損失、ポイントは?
ソフトウェアの新バージョンの発売にあたり、
旧バージョンは販売を行わない見込みとなった場合、
資産性が失われたものと考えるため、費用または損失処理を行います。
新バージョンが旧バージョンのソフトウェアに対する改良により制作されたのであれば、
旧バージョンに対する資本的支出として処理します。
税法上、市場販売目的のソフトウェアについては、
資産性が失われた状況を合理的に説明できるよう、
販売終了の意思を示す稟議書や代替する新製品の開発稟議書や企画書、販売業者への通知書等を具備することで、除却年度における損金算入が可能となります。
通常、製品の販売後に生じた不具合への対応のため、
サポートサービスが用意されています。
無償のサポートサービスは人件費や経費の発生がしますので、
こちらは通常の維持管理に要する費用として損金として処理します。
匠税理士事務所の渋谷・港のIT事業支援サービス
匠税理士事務所では、
渋谷・港を中心にIT企業の方の経営支援や税務コンサルティング、
会社設立などの起業支援を行っております。
サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。