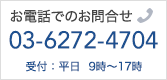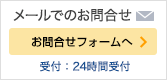弊所では相互リンクを募集しています。
原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)
しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。 なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。
(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)
なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。
HP1について
URL https://www.takumi-tax.jp/
サイト名:税理士 世田谷区 でリンクをお願いします。
紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
HP2について
サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。
相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
(サイト名は上記のままでお願いします。)
ご連絡お待ちしております。
以上、宜しくお願いします。
何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。
補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。
宜しくお願いします。
税理士 世田谷区 の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ