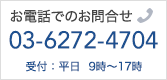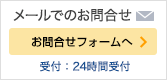消費税の改正により基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかどうかに加えて、
特定期間の課税売上高又は給与等が1,000万円かどうかという点で
消費税の課税事業者か免税事業者かを判定することとなりました。
この際の給与とは、どこからどこまでをいうのでしょうか。
消費税法では下記のように規定されています。
(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額)
1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、
特定期間における課税売上高又は
法第9条の2第1項
《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の
個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った
所法第231条第1項《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する
支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして
財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。
この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、
所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号に規定する
給与等の金額をいうことから、
当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、
所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。
(平23課消1-35により追加)
(注) 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。
この規定によると給与等は基本的に所得税法でいう
給与等が該当すると規定されています。
つまり、所得税法上の給与は、給与としてカウントし、
所得税がかからないような通勤交通費や、旅費などは給与から除くものとしています。
また注意書きとして、未払分は含まないとの規定がありますので
こちらもあわせて経理や申告では注意をしたい点です。
サービス内容
---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 渋谷区 税理士 匠税理士事務所
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------
世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。
大田区 税理士匠税理士事務所ホームページへ